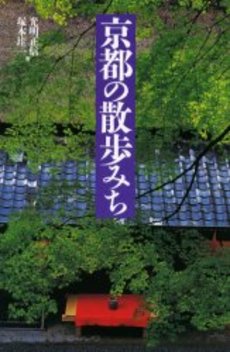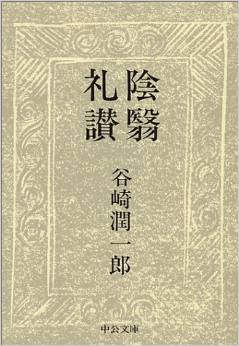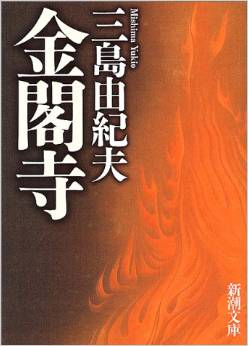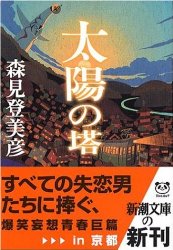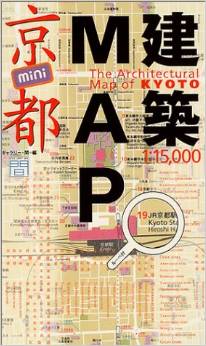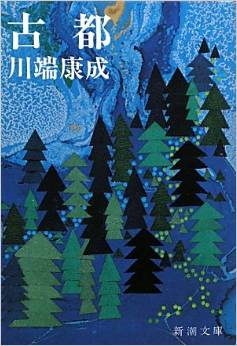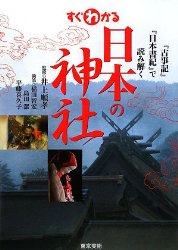京都の本
京都を描いた本や、京都にまつわる本で著作権が切れたものをフルテキストで紹介します。
このページを最初に作ってから、15年近くが過ぎ、当時から何度か試みては失敗していた縦書表示ができるようになりました。
テキストは青空文庫からお借りしてます。

善の研究
西田幾太郎
「哲学の道」の由来となった「哲学」ってどんなん?って思ったりしますよね?
こんな感じです。
スティーブジョブズほか、世界中に影響を与えた禅僧、鈴木大拙も西田の同窓でした。
一時期人気のなかった京都学派も最近は再び注目されつつあります。

祇園の枝垂桜
九鬼周三
短い随筆。
周囲に見苦しい花見客がいても、土産物屋や料亭が俗悪でも、それでもなお円山公園の枝垂れ桜はスバラシイとのこと。
当時とは代が違いますが、それでも春の円山公園の雰囲気は独特のものがあります。

虞美人草
夏目漱石
冒頭に雲母坂(きらら坂)(修学院のあたり)、比叡山、そして嵐山。
大原女とすれ違うことはもう多分ないだろうけど、平八茶屋はいまでも山端にあります。
『春はものの句になりやすき京の町を、七条から一条まで横に貫つらぬいて、煙けぶる柳の間から、温ぬくき水打つ白き布を、高野川磧に数え尽くして、長々と北にうねる路を、おおかたは二里余りも来たら、山は自から左右に逼って、脚下に奔る潺湲(せんかん)の響も、折れるほどに曲るほどに、あるは、こなた、あるは、かなたと鳴る。山に入りて春は更ふけたるを、山を極めたらば春はまだ残る雪に寒かろうと、見上げる峰の裾を縫うて、暗き陰に走る一条ひとすじの路に、爪上つまあがりなる向うから大原女が来る。牛が来る。京の春は牛の尿の尽きざるほどに、長くかつ静かである。』
美文です。
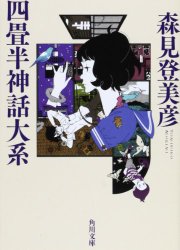
四畳半神話体系
森見登美彦
森見登美彦は京都大学農学部出身。左京区の怠惰な感じを書かせたら右に出るものはいない。京都の京都らしさがすばらしいですが、この本の内容は、イーガンと左京区が四畳半で出会ったみたいな。